最近、文部科学省や厚生労働省が公開している30年間の大卒就職率・有効求人倍率の推移データを改めて目にする機会がありました。その中で1999年の就職率が「72%」と示されていたのですが、私の記憶や実感とは大きく乖離があり、驚かされました。

「72%もあったのか?」
「いや、体感では半分も就職できていなかったぞ?」
そう感じた私は、この数字の裏側と、実際に氷河期世代が直面していた就職活動のリアルについて、今一度考察してみることにしました。
「就職率72%」という数字のからくり
まず、就職率という統計の定義を確認してみましょう。
就職率 = 就職希望者のうち、実際に就職できた人の割合
一見、正確に見えるこの数値ですが、実は以下のような人たちは「分母に含まれていません」。
• 大学院に進学した人
• 公務員試験を目指して浪人した人
• 就職活動自体を諦めた人
また反対に
• 非正規雇用は雇用されたとカウント
このような集計の仕方では、実態よりも良い数字が出てしまうのは当然のこと。72%という数字が現実の肌感覚と乖離している理由も、ここにあるのではないかと思います。
本当に厳しかったのは「数字に出ない部分」
就職氷河期が厳しかったとされる最大の理由は、ただ単に「就職できたか否か」ではありません。その“中身”にこそ、深刻な問題が潜んでいたのです。
1. 初職が非正規の人が多数
1999年当時、正社員として就職できる人は一部に限られ、多くの学生が契約社員、派遣社員、アルバイトといった“非正規雇用”で社会に出ていきました。
一度非正規として働き始めると、次の転職やキャリアアップが非常に困難になります。結果として、長期的なキャリア形成が阻まれ、生涯賃金にも大きな差が生まれることになりました。
2. 希望職種や業界に就けず、“妥協就職”が当たり前に
当時は、超一流大学の学生ですら「どこでもいいから内定がほしい」という空気が支配していました。自分の希望職種や業界にこだわる余裕はなく、多くの学生が「生き残るため」の就活を強いられていたのです。
私自身、希望していた業界は複数ありましたが、途中からは「とにかく正社員として雇ってくれるならどこでもいい」という心境に変わっていったのを今でも覚えています。
3. 面接数十社、エントリー数百社も当たり前
「氷河期世代は、行動力が足りなかった」といった言説も時折見かけますが、それはあまりにも的外れです。当時は、面接に30〜50社、エントリーに至っては100〜200社というのも珍しくありませんでした。
それでも「内定ゼロ」で卒業する学生も少なくなく、いわゆる「既卒」という不利な立場での再スタートを余儀なくされるケースが後を絶ちませんでした。
4. 企業の採用数そのものが激減
バブル期には、企業が新卒を数百人単位で採用していました。しかし、就職氷河期のころにはその数が一気に一桁〜数十人にまで減少しました。これは企業側の都合による「採用抑制」が背景にあります。
つまり、求職者が増えたから競争が激しくなったのではなく、「受け入れ口」そのものが極端に減っていたというのが本質なのです。
官僚や政治家にとって「数字は自分たちの評価」
統計には「意図」が入る、という話を最後にしておきたいと思います。
たとえば、政府や官僚にとって「就職率が高い」という数字は、景気が良く、政策がうまくいっているという“アピール材料”になります。逆に悪い数字は極力出したくない。だからこそ、集計方法や定義の工夫によって“都合の良い数字”が世に出されることもあるのです。
「見せたい現実」を作るために、「見せ方」を変える。
これが統計という道具の怖さでもあります。
終わりに:数字の裏にある“人間のドラマ”を忘れないでほしい
私はあの時代に、就活を通して多くの理不尽を味わいました。しかし、それは私個人だけの体験ではなく、「氷河期世代」の多くが共通して経験してきた現実でもあります。
表面的な数字では、その苦しさはなかなか伝わりません。だからこそ、こうして言葉にして発信することに意味があると考えています。
当時の私たちが直面したのは「たまたま運が悪かった」では済まされない、社会構造的な問題でした。もし、あなたの周囲に氷河期世代がいたら、ぜひその背景にも思いを馳せてみてください。


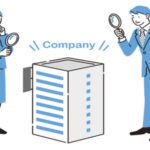
コメント